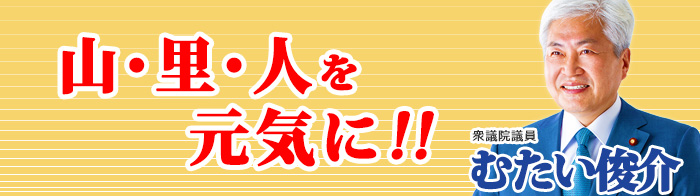理念・政策・メッセージ
2025.09.25
「居住集合住宅での夕涼み会企画で感じたこと」
〜大災害時の円滑な助け合いへの架け橋〜
酷暑が過ぎ、秋らしさが漂う9月21日の午後、松本の居住集合住宅の夕涼み会を初開催しました。9年前に竣工した松本市の高台に建つ93世帯が入居する集合住宅に入居したのは、2024年の2月。安曇野市の自宅が古くなり、断熱機能が弱くなっていることから、妻が松本のマンションを探し、辿り着いたのがこの集合住宅でした。この結果、私にとって、安曇野市の自宅、松本市の居宅、東京渋谷の居宅と3か所の住居を抱える結果になっています。
この3か所の自宅を行き来し、管理することは結構大変です。特に、庭のある一戸建ての安曇野市の自宅は、草刈り、掃除、郵便物・回覧板の管理が大変です。松本市の居宅では犬を飼っており、毎日の散歩の役割を私が果たしていることから、松本に滞在する機会が多くなっています。東京代々木の自宅は、上京して仕事をこなす際に拠点として便利に使っています。東京に居宅が無ければ、現在の活動は継続できないと感じています。
それぞれの居住地でそれぞれの地域との関係があり、できるだけ対応するようにしています。安曇野市では隣組長を務めました。東京のマンションも管理組合の理事を経験しました。そして、松本市内のマンションでは、今年から管理組合の副理事長を務めています。
数か月前に管理組合の理事会を開催する中で、隣に誰が居住しているか分からないまま過ごしている現状の中で、何かあった時の支え合いが必要になった際に円滑にその助け合いが可能となるには日常的な円滑な人間関係が欠かせない、そのためには、例えば広いマンションの中庭のスペースを生かし、夕涼み会といったイベントを開催し、緩やかなお付き合いが可能となる機会を持ったらどうかという提案が行われ、理事会中心に企画していくことになりました。
子ども達の参加、マンション住人の飼っている犬の参加も大歓迎、焼きそば、飲み物、果物の提供を前提に93世帯の皆様に声を掛けました。食事の提供も伴うことから保健所への相談、近隣の皆様への情報提供、買い出し、備品の準備、お楽しみイベントの企画など、理事会で揉みました。
若手理事の一人が、実行責任者を買って出てくれ、彼の周到な手配があったこともあり、企画はスムースに進みました。管理規則の中で、共有スペースでの犬の歩行は禁止されていることから、イベント中は区域を限っての歩行禁止解除をする理解もマンションの皆様に納得いただく手続きも経ました。
結果として、93戸のマンションの52戸90人以上、犬7匹が参加。参加率は戸数ベースで6割となり、予想以上の盛会となりました。子供の参加も非常に多く、和やかな夕涼み会になりました。前日の雨もその日は秋らしく涼しい天気にも恵まれました。多くの参加の皆様が2時間の開催時間いっぱいに現場に留まって頂けました。
7匹の犬は、子ども達に愛嬌を振りまき、我が家のスーも皆様に可愛がられ、しっぽを大きく振りいつも以上に興奮して遊びまわっていました。
マンションの管理会社の方も参加され、差し入れもいただきましたが、その管理会社が取り扱っている案件で今回のような企画が実現したということは聞いたことが無いと驚いていました。
集合住宅は、どちらかというと匿名性が高く、むしろそれを是とする感覚がありましたが、今回の企画により、相当数の皆様が、実は緩やかな形の触れ合いを求めているということも知ることができました。
こういう企画の発想に至ったのも、実は、毎朝の犬の散歩で、犬を通じた世間話の延長線上で実現したとも言えます。その意味では、生活の中でさりげない隣近所の触れ合いのきっかけとしてペットの位置づけの重要性も再確認しました。我が家のスーも、重責を果たして、その日はぐっすりと休んでいました。
国会議員を退任し、地域社会で日常生活を過ごす中で、これまでの仕事中心の生活の中では見出せなかった生活の質向上という別次元の価値を探し出せた思いを噛みしめています。そして、このような緩やかなつながりが、必ず大災害時の円滑な助け合いに繋がる架け橋となるということも、強く認識しました。