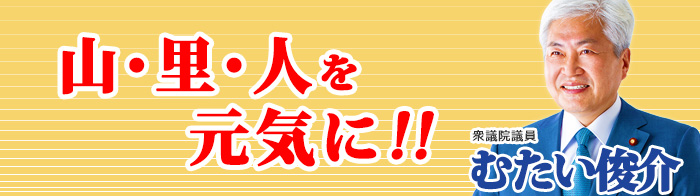理念・政策・メッセージ
2025.07.23
「「引かれ者の小唄」から始める自民党の再構築論」
〜若返りと価値観の再定義を問う選挙総括〜
7月20日に催行の参議院選挙の結果が判明しました。予想通りの自民党公明党の与党が歴史的敗北を喫し、衆議院に次いで参議院でも与党は過半数割れという異常事態となりました。
国際環境が緊迫度を増し、メリハリのある迅速な政治的意思決定がますます必要とされる中で、それが阻害される混沌の政権運営を余儀なくされる事態を招来してしまいました。国民がその混沌を望んだとは言えないにしても、結果的にそうした国民の判断を招いたことに、政権与党の幹部は猛省しなければなりません。
結果を概観すると、与党の退潮に対して、保守的な主張を展開した国民民主党、参政党が大きく党勢を伸ばした一方で、立憲民主党は現状維持、共産党は半減と革新勢力も退潮と言える結果となりました。分かりやすく解説すれば、自民党がリベラル政策をとる中で、保守層が自民党を見限り、国民民主党、参政党に票が流れたという構図が見て取れます。
保守的な主張を掲げて立候補した自民党公認候補も、自民党の中で保守的主張をしても有権者の投票行動に繋がらず、軒並み落選の憂き目にあいました。この結果、自民党自体が更にリベラル化する可能性も考えられます。自民党が、保守からリベラルまで幅広い考え方の議員を抱えて、包摂度の高い党運営を出来た時代は過ぎ去ったのかもしれません。
価値観の異なる立場で個別政策毎に賛否が分かれ、それが大きな争点となり、政治的対立が激しくなる。それを一つの政党の中で収斂した対応をすることは難しい時代になりました。選択的夫婦別姓、皇位継承に関する対立はその象徴なのかもしれません。
欧州各国も政党が多元化する傾向が生じています。SNSを通じて瞬時に情報が共有され、しかも意図的に自分たちの主張に誘導するフェークニュースが氾濫する中で、人々の考え方は漂流する傾向が強くなって行くように思われます。こうした時代に、人々の怒りや激情に火をつけそれに油を注ぐ扇動者が現れてもおかしくはありません。我々は、情報の真偽を見極め、扇動者の意図を見極められるリテラシーを高めなければなりません。そうでないと、民主主義は壊れます。
私の地元の長野県では、35歳の女性自民党候補が立憲民主党の男性候補に敗れました。長野県の有権者の皆様は、普段から「世襲は良くない」、「政界への女性の進出が少なすぎる」という論点に共感していますが、いざ選挙になると、政治的背景のない非世襲の若い有能な女性が出馬しても、自民党候補であるという理由で、真反対の投票をする結果となりました。それでも、自民党候補の票と参政党候補の票を合わせると当選者の票を大きく上回るのですから、左翼陣営が候補を統一したことに対し、保守陣営が分裂した構図の選挙が、長野県においては自民党に極めて不利に働いたという背景はあります。
与党自民党をどのように立て直していくべきか、早急に考えなくてはなりません。政策の吟味選択はもとより、中央政界も地方政界も、いわゆる「政治に長く携わっている中高年齢層の政治家」が多すぎること、そのことが有権者の飽き、厭倦感に繋がっていることを意識しなくてはなりません。
選挙戦の途中で、長野県選挙区で立候補の藤田ひかる候補が、居並ぶ自民党国会議員、地方議員を前に、「皆様には申し訳ないが、自民党のイメージは、背広を着た中高年の男性議員で占められていること。若い世代の声が伝わっていないと感じているからこそ、私は立候補した」と勇気ある気持ちの吐露をしていました。それが世間一般の声だと私も感じます。しかし皮肉なことに、その会場には若い世代の姿はまばらで、殆どが中高年の男性有権者だったのです。
自民党政治の出直しは、当選回数の長い議員が、男女問わず若手にバトンを渡すことから始めるべきだと考えます。そのためには期数制限などの制度化も含め、思い切った体質改善が不可欠だと感じます。中高年議員による「変わります」という宣言ほど空疎に響くものはありません。有権者の耳には、それはまるで「引かれ者の小唄」のように聞こえてきます。今こそ、「身を捨ててこそ浮かぶ瀬もあれ」、です。真の改革とは、自ら退くことに始まるのことも往々にしてあります。