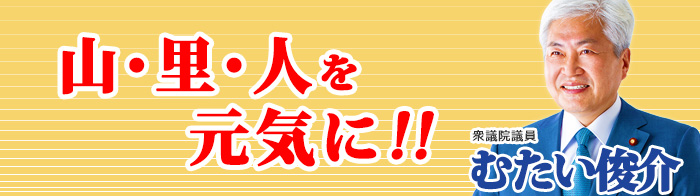理念・政策・メッセージ
2025.07.11
「消費税減税について考えること」
(給付面の位置づけも踏まえた議論を期待)
消費税減税が参議院選挙の最大の争点になっています。与党が、給付金対応で物価高対策を訴えているのに対し、野党は全党が消費税引き下げを訴えています。この点についての私の考えは、複雑な心境です。
確かに、物価高に所得の伸びが追い付かず、実質所得がマイナスになっている中で、国民負担を減らす消費税減税は受け入れやすい提案のようにも思われます。特に、食料品への消費税減税は多くの国民の日々の生活に直結する提案であり、賛同する皆様も多いと思われます。私も食料品を中心とした消費税減税は、全く否定すべきものだとは思いません。
一方で、消費税はシステムが非常に複雑です。消費型付加価値の消費税は、転々流通する流通段階でそれぞれ前段階の課税分を控除し消費税の納付を求められます。ただでさえ複雑なシステムに軽減税率や非課税の仕組みを組み込むことは、十分な準備と一定期間が必要です。財務省は、混乱なく減税をするのに必要な時間について「一年は欲しい、半年では難しい」との調査結果を明らかにしています。
本来であれば、選挙の都度、有権者の感性に訴える形でこうした争点が浮上することは望ましいものではありません。消費税はその本質は社会保障財源です。社会保障の在り方を見据え、その財源としての消費税をどのように位置づけるかという観点が必要ですが、残念ながら今回の参議院選挙においては、そのような俯瞰的な議論はなく、負担軽減一辺倒の議論に偏っています。社会保障と税の一体改革を総理としてまとめた野田佳彦立憲民主党党首ですら、社会保障全体を見据えた議論を捨象し、負担軽減に没入した議論をしているのは、残念です。
消費税減税の最大の問題はいったん減税すれば元に戻せない可能性が高いということです。諸外国でもそうした事例が相次いでいます。それはそうです。戻す際には増税になるのですから政治的リスクは大きくなります。市場関係者の視点はその点を認識し、一度減税すると再増税はできないとの想定で市場は動き、海外勢が日本国債売りに廻るリスクがあると見ています。現に、参議院選挙で消費税の負担引き下げが争点になっていることだけで、日本国債の長期金利が跳ね上がるという現象が起きています。その結果、金利は上がり、国民生活には大きな負担が生じます。この点は、英国で大幅減税を発表したとたんに英国国債が売られ、ポンド安が生じ、時の政権が崩壊した事例もあります。
ここで、あまりマスコミで取り上げられない視点を紹介したいと思います。消費税を5%に上げる際にその1%分を地方消費税として国税から独立させた際に、その制度改正を実務面で担った旧自治省税務局の担当課長補佐であった私の立場からすると、消費税の収入が地方自治体の重要な安定財源になっていると追うことを忘れるべきではないと指摘したいと思います。大きな意味での消費税は、地方消費税、地方交付税といった形で地方自治体の基幹的収入になっています。地域医療、介護・福祉などが消費税によって支えられているのです。消費税の在り方を議論する上では、その負担の側面とそれがどのような形で国と地方によって使われているかについても注視する必要があるということです。
若者と高齢者にとって消費税減税がどのように受け止められているかも重要な論点です。一般的には若い世代ほど消費税減税に賛同する傾向があるように報じられています。しかし、我々が消費税を議論した時代には、資産は多いがフロー所得が少なくなる高齢世代に負担を求める手段として消費税の役割は小さくないし、それが世代間の公平確保に資するという認識が一般的でした。消費税の使途である社会保障の受給側に立つのも高齢者が圧倒的に多いのです。
アメリカのトランプ政権は、「一つの大きく美しい法案(OBBB)」を成立させました。巨額の減税法です。この法律を後押しした勢力は、「この法律によって経済成長が実現し全ての問題が解決される、成長が加速すれば債務負担が軽くなり、雇用の増加や賃金の上昇を通じて低所得者に利益がもたらされ経済面から政治機能の不全が解消される」(英国エコノミスト誌)と主張しますが、この経済政策によって「債券市場が急変しその圧力から財政政策に修正を迫られるとそのコストは膨大になる」、「OBBB法は長期的視点を欠いている」(英国エコノミスト誌)とも指摘されています。
今回の参議院選挙では、日本でもさながらトランプ政権の政策のミニチュア版の議論が行われていますが、良識の府参議院にふさわしい目先の議論ではない骨太の議論を期待したいところですが、現実は厳しいですかね。