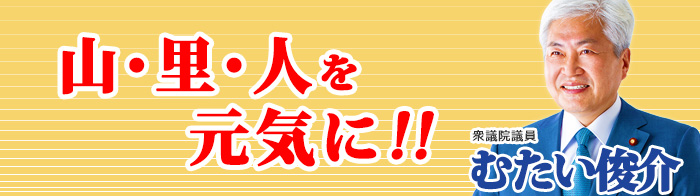理念・政策・メッセージ
2025.02.21
「ウクライナ訪問の結果報告」
〜義を見てせざるは勇無きなり〜
2月9日に日本を発ち、ロンドン、ワルシャワを経由し、11日から13日の2泊3日の短期滞在ながらもウクライナのキーウを訪問する機会を得ました。戦時下のウクライナ訪問は、外務省により渡航禁止の布令が出されていますが、復興関係の用務があれば安全対策を講じた上での限定的な訪問が例外的に許されるという切り口を探り、何とか訪問が実現できました。それでも、滞在期間中、ロシアによるキーウへのミサイル攻撃があり、我々も宿泊場所のホテル地下のシェルターに2度駆け込みました。その時のミサイル攻撃ではキーウで1名が犠牲になったと翌日伺いました。
今回のウクライナ訪問の目的は、日本の災害復興の経験を活かし、それをウクライナの戦災復興に役立てることにありました。様々な支援手法がある中で、我々の切り口は、機能性と環境負荷の低さに優れたトレーラーハウスに注目し、その活用について関係者と議論を行うことでした。4名の訪問団は、トレーラーハウス製造会社、トレーラーハウスを所有し実際に災害現場でそれを活用している防災ボランティアの方、そしてシェルター整備の専門家に私を加えたチームでした。
日本ウクライナ友好議員連盟の会員を含むウクライナ国会議員10名、経済省、ウクライナ投資庁、復興庁、避難民支援委員会、商工会議所の幹部の皆様が我々の提案に耳を傾けて頂きました。更に、駐ウクライナ日本大使館、駐ポーランド日本大使館、JETROの関係者ともお話をすることができました。
今回の訪問で改めて感じたのは、ウクライナ側の日本の支援に対する感謝の気持ちが大変強いことです。遠く離れた極東の日本が、何故破格の支援を国を挙げてしてくれるのか、その理由を尋ねられるほどでした。このやり取りを通じて感じたことは、例えばトランプ大統領がウクライナ支援にあからさまな見返りを求めているのに対し、日本の支援は直接の見返りを求めることが無いことに、先方が感動しているのではとすら感じる局面がありました。
ひょっとしたら、これこそが武士道の精神ではないか、と私には思えました。「義を見てせざるは勇無きなり」、或いは「弱きを助け強きを挫く」という言葉に代表されるのが日本精神です。今のロシア、中国、更に言えば米国ですらその言葉の精神とは真逆の行動に出ていることは嘆かわしい限りです。
ところで、ウクライナで意見交換を行った皆様との議論は概ね以下の通りでした。今回の訪問は、これからの広範な日本の復興支援の出発点になって欲しい、出発点にするのだ、と願い、誓っています。
1. トレーラーハウスの活用とその利点
日本では、能登半島地震などの災害を通じて、仮設住宅の代替手段としてトレーラーハウスの導入が進んできています。最近では、水循環システムを進化し、水利の環境が悪いところでもトレーラーハウスを設置できるシステムが開発導入されています。今回、トレーラーハウスについて、ウクライナ側でも以下のような利点について認識共有がなされました。
・設置コストの低減:一般的な仮設住宅よりも低コストで導入可能。
・機動性:必要な場所へ迅速に移動・設置ができる。
・快適性:床暖房などの設備により、寒冷地でも快適な居住空間を提供。
・資源の有効活用:不要になった場合も再利用可能で、廃棄コストがかからない。
2. 日本の防災経験の共有とウクライナ復興への応用
日本は災害大国であり、その経験を活かした防災・復興支援の知見をウクライナに提供可能ですが、具体的には以下の点について議論がなされました。
・災害時の即時対応:日本ではトレーラーハウスを平時から備蓄し、有事に活用する仕組みを検討している。これをウクライナの復興計画にも応用可能。
・自律循環型システム:水の循環システムを備えたトレーラーハウスを活用することで、インフラが破壊された地域でも独立した生活が可能。
・防災庁の役割:日本で進行中の防災庁構想を参考に、ウクライナの復興支援における官民連携の可能性についても議論。
3. シェルター整備の視察と日本への示唆
ウクライナでは、戦時下においてシェルターの存在が改めて重視されています。一方、日本では地下シェルターの整備がほとんど進んでおらず、沖縄県でようやく整備が始まったばかりです。今回の訪問では、ウクライナのシェルターの実際の機能を視察し、その知見を日本の国土強靭化の備えに活かす可能性についても検討しました。
4. 日ウクライナ友好議員連盟との交流
訪問の一環として、ウクライナ側の議員連盟メンバーとの会合が行われました。ここでは以下の点が議論されました。
・ウクライナの復興支援における日本の役割
・地域レベルの交流促進:例えば、日本の朝日村でウクライナ産ビーツを栽培し、ボルシチのレトルト食品を製造する取り組みの紹介し、ビーツを介した自治体交流の可能性も議論。
・人的交流の強化:将来的な復興を見据えた日ウクライナ間の人的交流の可能性について。
5. ウクライナ復興に向けた隣国ポーランドの役割
ウクライナ復興に向けた国際的な取り組みは、多くの国々の協力によって支えられています。その中でも、隣国ポーランドはウクライナ難民の最大の受け入れ国であり、人道支援やインフラ整備の面でも大きな貢献を続けています。さらに、ウクライナへの軍事・経済支援を積極的に行い、EUやNATO内での調整役としても機能しています。復興の過程においても、ポーランドの関与は不可欠であり、両国間の経済的結びつきが強まる中で、ポーランド企業がウクライナの再建プロジェクトに関与する機会が増えており、エネルギー供給やインフラ再構築の分野での協力が期待されます。このように、ポーランドはウクライナ復興の要となる国の一つであり、日本も復興支援に当たって、ポーランドとの連携の模索が選択肢の一つに上がると思われます。
6. 今後の展望
今回の訪問は、ウクライナ復興支援のための第一歩であり、今後さらなるネットワークの強化と具体的な支援策の検討が求められます。日本独自の災害対応技術を活かし、ウクライナの復興に貢献することが重要であり、戦時下の中でも、できることについては早期の対応検討が期待されます。