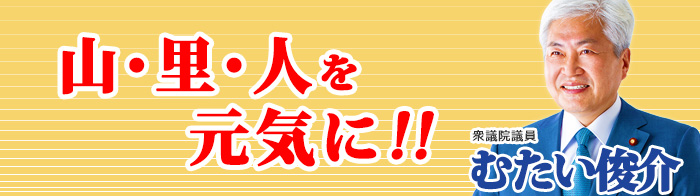理念・政策・メッセージ
2025.02.11
「ウクライナ訪問の目的」
〜日本の資源で復興支援〜
2月の中旬にウクライナのキーウを訪問することとしました。ポーランド経由で訪問してまいります。外務省のガイドラインに沿って、外務省のご理解を頂き、戦時下の首都を訪問する意味をわきまえて、安全対策には万全の対応をしての訪問となります。
ロシアのウクライナ侵略後、日本国民の間ではウクライナに対し国民を挙げて同情の気持ちが満ち溢れています。今回のロシアによるウクライナ侵略については、日本は人道上の観点、正義という観点に加え、ロシアの暴挙が見過ごされることになると辛うじて保たれている現在の国際秩序が根底から覆され、中国などの独裁国家に対して誤ったメッセージを送ることになりかねないとの思いが広く国民の間に共有されているためです。
それでもなお、日本は憲法上の制約があり、軍事的な支援はできないことになっています。一方で、ウクライナの国民を守る地対空ミサイルなどの迎撃用兵器くらいは何とかならないかとの意見もありますが、今の日本の政治状況でそれを直ちに決断していくことは難しいように思われます。いずれにしても、人道的、復興時の支援については、わが国には様々な分野で支援できる能力と資源が備わっています。
私は衆議院議員をやっている間、森英介会長の下で日本ウクライナ友好議員連盟の事務局長を務めさせて頂きました。ウクライナ支援の為に松本駅前で何度も募金活動を行いました。昨年2月にはウクライナのシュミハリ首相を国会にお迎えし、超党派の議員連盟でウクライナ支援について話し合いも行いました。その際に、ウクライナ支援については、与野党問わず全面賛成であるというメッセージをお伝えすることが出来ました。
ロシアによる執拗な軍事攻撃の中で、現在のウクライナを巡る状況は厳しさが増していと認識しています。しかし、平和が訪れるであろう時に備えて、我々も手を拱いて待っているわけにはいきません。
今回の訪問は、考えられる数ある日本の支援策の中でも、新たな日本の技術アイデアの進歩について情報を共有しようというものです。その一つとして、トレーラーハウスを活用した機動的な復興支援をご紹介したいと考えています。日本は災害大国です。災害対応、復旧、事前準備については、大きな蓄積があります。被災地での被災者の生活支援の一環として仮設住宅の建設が日本では一般的ですが、そのコスト、スピード感に課題があり、最近ではトレーラーハウスを活用した被災者支援が注目されています。私も能登半島地震の際に、その投入の手伝いをしてきました。
トレーラーハウスは需要に応じてどこにでも赴くことが出来ます。おまけに最近の技術の進歩で、水の循環システムが研究され、上下水道に繋ぐことなく、自律独立循環型で稼働する仕組みが生み出され、実装されています。今回のウクライナ訪問ではそのシステムのご説明に伺います。トレーラーハウスの活用は、住宅事情に困難を抱えるウクライナの国民にとっても、そして復興支援の為に駆け付ける日本の人々にも極めて利便性の高いものと考えています。ウクライナ側でもこうしたシステムの存在について今の時点から認識頂けるように努めたいと考えています。
今回の訪問では、ウクライナにおけるシェルターの機能についても注目しています。ウクライナはシェルター大国だと認識しています。戦時下でシェルターの存在感が際立っていると思います。一方、日本では地下シェルター整備がほとんど進んでいません。私は、シェルター整備の議員連盟の事務局長もしていましたが、議員連盟の動きもあり、漸く、中国と国境を接する沖縄県での整備が始まったばかりです。今回は、戦時下におけるシェルターの実際の機能についても具に見て参りたいと考えています。
今回の訪問では、日本ウクライナ友好議員連盟のウクライナ側のメンバーとの会合も予定されています。前議員連盟の事務局長の立場としては、まず、ウクライナ側の議員連盟の皆様のお気持ちを、日本側議員連盟にお伝えすることを想定しています。また、日ウクライナ政府間の交流に加え、議員連盟としての交流も重要であると考えています。実は私の地元の朝日村では、ウクライナ名産のビーツを栽培しており、そのビーツを原料にボルシチを作り、レトルトにして販売しています。朝日村では、いずれ平和が訪れた際にビーツの産地との交流をしたいとの希望もあります。そういう地域レベルの関係強化も視野に入れて息の長いお付き合いをしてまいりたいと思っており、議員連盟の皆様にはその橋渡し役も期待しています。
6日には、永田町で訪問団の結団式も行いました。キーウ出身の国際政治学者グレンコ・アンドリー氏からウクライナ戦争の今後の展望について、ロシア側の本質的な狙いを見据えた冷静な見方を伺いました。ロシアとしては、ウクライナ全土を掌握することが目的であり、停戦案もその目論見に沿ったものでなくては受け入れない、仮に停戦が実現するとしたら、戦っても占領地が拡大する見通しが立たないこと、戦費が枯渇することといった外的な事情がない限りは戦争は続くとの見立てを披露していました。その意味では、復興支援と言っても、戦時下の復興支援という限定された支援活動にならざるを得ない、とのご指摘をいただきました。それでもなお、現時点で訪問する意義はあると考え、行ってまいります。